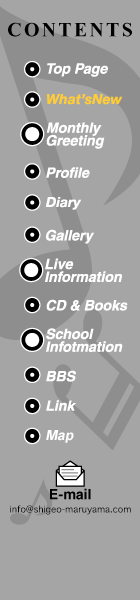

Diary = 日記という名前にしましたが、毎日書く訳でもなく、書きたくなったら書きたいように書くという態度で進めたいと思っております。したがって形式もテーマも、全体的に は、不統一なものになることと思いますが、それでかまわないと思っております。 ぼくの生活を書くわけですから当然、音楽のことが多くなることと思います。趣味の読書や釣り、料理や酒、旅の話題なども多くなることでしょう。時には、研究の中間発表のよう なものとなるやもしれません。また時には、以前に新聞の連載コラムやスイング・ジャーナルなどの雑誌に書いたものと内容が重複することもあるかもしれません。それもそれでま た、かまわないと思います。50を過ぎて、かつて自分が感じ入り、書き残したものを振り返り、再点検したいという思いもあります。 なにとぞ末永くおつきあいのほど、お願い申し上げます。 さらに、皆様に読んでいただくことを前提にしたページですから、多少でもお心に届く文章がございましたら、感想をBBSのページにお寄せいただければこれに勝る喜びはありま せん。 |
|
|
|
|
|